このように心得て唱える題目の功徳は、釈尊の功徳とまったく同じです。経には「阿鼻地獄の苦しみもすべて仏の境涯に含まれ、毘盧遮那仏の身と国土も凡夫の一念を超えるものではない」と説かれています。十四の誹謗の心については、経文に従って推し量るべきです。
このように法門をお尋ねになることは、まことに後世を願っておられる方であります。経には「よくこの法を聴く者は、これまた得がたい」と説かれています。この経は、正しい仏の使いが世に出なければ、仏の御本意のままに説くことは難しい上に、この経の意味を問い尋ねて疑いを晴らし、よく信じる者もまた得がたいと示されております。
たとえどんなに身分の低い者であっても、自分より少しでも智慧のすぐれた者には、遠慮せずにこの経の意味を問い尋ねるべきです。ところが、末法の人々は我慢や執着、名誉や利益にとらわれてしまい、「自分があの人の弟子になるなんて。もし教えを受けたら、人に軽く見られるのではないか」と、常に悪しき心にとどまり、ついには悪道に堕ちるのです。法師品には「八十億劫もの長い間、あらゆる宝を尽くして仏を供養する功徳よりも、法華経を説く僧を供養し、後にほんのわずかな時間でもこの経の法門を聴聞するならば、私は大いなる利益と功徳を得ると喜ぶべきである」と説かれています。智慧のない者であっても、この経を説く者に仕えることで功徳を得ることができます。たとえどんな鬼や畜生であっても、法華経の一偈一句を説く者を「必ず立ち上がって遠くから迎えるべきであり、仏を敬うようにすべきである」と説かれている道理に従えば、互いに仏のように敬い合うべきです。たとえるなら、宝塔品の時に釈迦仏と多宝仏が互いに敬い合ったようにすべきなのです。
この三位房という人物は身分の低い者ですが、ほんのわずかでも法華経の法門を説く者であるならば、仏のように敬って法門をお尋ねになるべきです。「法に依って人に依らざれ」という教えを心に留めておくべきです。
さて、昔ひとりの人が雪山という山に住んでいました。その人の名を雪山童子といいます。蕨を折り、木の実を拾って命をつなぎ、鹿の皮を着物に仕立てて身にまとい、静かに仏道を修行していたのです。
雪山童子が思ったことは、「よくよく世間を観ると、生死は無常の理であるので、生まれた者は必ず死ぬ。だから、この苦しみの多い世のはかなさは、まるで電光のように一瞬であり、朝露が日の光でたちまち消えてしまうようなもの。風の前の灯火が消えやすく、芭蕉の葉が破れやすいのと異なることはない。人は皆、この無常から逃れることはできず、最後に一度はあの世へ旅立つ。その死後の旅路を思うと、暗くて真っ暗であり、太陽や月や星の光もなく、せめて灯火さえもない。その暗い道に、共に行く人もいない。この世では、親類や兄弟、妻子や眷属が集まり、父は慈しみの心が深く、母は悲しみの情けが厚く、夫婦は海老が同じ穴に住む契りのように、一生を一緒に過ごして離れることがない。鴛鴦が同じ布団の下で枕を並べて戯れるように仲むつまじいのだが、あの死後の旅路には共に行くことはない。暗い道をただ一人で行く。誰が来て善悪を導いてくれるだろうか。また、老人と若者、どちらが先に死ぬかわからない世の中であるから、老いた者が先立ち、若い者が残ることもあり、これは順序通りの道理。その嘆きの中にも、せめて慰めとなることもある。しかし、老いた者が残り、若い者が先立つこともある。最もつらいのは、幼くして親に先立つ子であり、最も嘆かわしいのは、老いて子に先立たれる親である。このように、生死は無常であり、老人と若者、どちらが先に死ぬかわからない世の中ははかないのに、人々は昼夜、現世利益のための行動ばかりに専念し、仏を敬わず、法を信じず、修行も智慧もなく、空しく日々を過ごしている。死後、閻魔の裁きの場へ引き出される時には、何を資糧として三界の長い旅を行き、何を船や筏として生死の広い海を渡り、実報や寂光の仏土に至るのだろうか」と思いました。「迷いの人生は“夢”。悟りに目覚めた人生こそ“現実”。ならば、この夢のような苦しい世の中を捨てて覚りの現実を求めよう。」と考え、雪山に籠もって観念の座に妄想や迷いを払い、ただひたすら仏法を求めていました。その姿を帝釈が遥かに天から見下ろして思ったことは、「魚の子は多いが、魚になるのは少なく、菴羅樹の花は多く咲くが、実になるのは少ない。人もまた同じである。菩提心を起こす人は多いが、退転せず真実の道に入る者は少ない。すべて凡夫の菩提心は、多くの悪縁に惑わされ、事に触れて移りやすいものである。鎧を着た兵士は多いが、戦に恐れを抱かない者は少ない。この人の志を試してみよう」と思い、帝釈は鬼神の姿を現して童子のそばに立ったのです。
その時は、仏が世におられなかったので、雪山童子はいくら大乗経を求めても、聞くことができませんでした。ある時、「諸行は無常である。これが生滅の法である」という声が、かすかに聞こえてきました。童子は驚いて四方を見渡しましたが、人の姿はどこにもありません。ただ鬼神が近づいて立っていました。その姿は険しく恐ろしく、頭の髪は炎のように逆立ち、口の歯は剣のように鋭く、目を怒らせて雪山童子を見守っていました。しかし童子はそれを見ても恐れず、ただひたすら仏法を聞けることを喜び、怪しむことはありませんでした。まるで母から離れた子牛が、かすかに母の声を聞いたような心持ちであったのです。
雪山童子は思いました。「このことを唱えたのは誰だろう。まだ残りの言葉があるはずだ」と思い、あたり一面をくまなく尋ね求めましたが、やはり人の姿はありませんでした。そこで童子は「もしやこの言葉は鬼神が説いたのか」と疑いましたが、「いや、そんなはずはない」と思いました。「あの姿は罪の報いによる鬼神の形である。この偈は仏が説かれた言葉である。こんな卑しい鬼神の口から出るはずがない」と考えました。しかし、他に人もいないので、「もし、この言葉を説いたのはあなたですか」と問うと、鬼神は答えました。「私に物を言うな。食べずに日数を過ごしたので、飢えて愚かになり、正しい心を保てない。すでに戯れ言を言ったのだろう。私が嘘をつくつもりで言ったなら、知ることもできないだろう」と答えました。
童子が言いました。「私はこの半分の偈を聞いたことは、半分の月を見たようであり、半分の玉を得たようなものです。確かにあなたが唱えたものでしょう。どうか残りの偈を説いてください」と。すると鬼神が言いました。「お前はもともと悟りを得ているのだから、聞かなくても恨むことはあるまい。私は今、飢え苦しんでいて、とても語る力がない。だから私に向かってこれ以上話しかけるな。」と。それでも童子は尋ねました。「食べ物を得れば、説いてくださいますか」と。鬼神は答えました。「食べ物を得れば、説いてやろう」と。童子は喜んで「では、何を食べ物とするのですか」と尋ねました。鬼神は言いました。「それ以上聞くな。その答えを聞けば、必ず恐ろしくなる。お前が求めるべき物でもない。」と。しかし童子はなおも尋ねました。「その食べ物が何であるかだけでも教えてくだされば、試しに探してみましょう」と。すると鬼神は答えました。「私は、ただ人の柔らかい肉を食べ、人の温かい血を飲むのだ。空を飛び回って広く探しているが、人々は仏や神によって守られているため、思うように殺すことができない。仏や神が見捨てた者だけを食べているのだ。」と。
最終パートに続きます。
📺 YouTube 日本語・韓国語・英語で対応🎥 Available in Japanese, Korean, and English
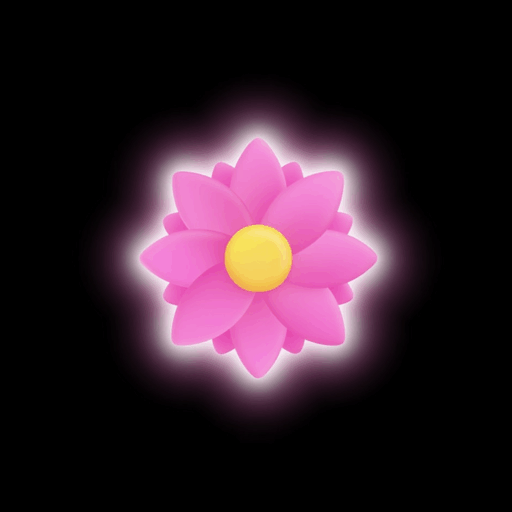
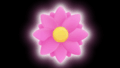
Comments